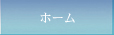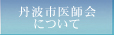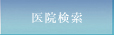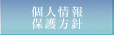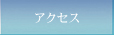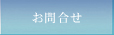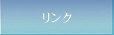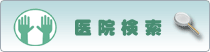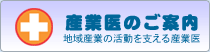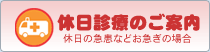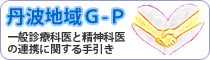予防接種のご案内
予防接種とは、病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチンを接種することをいいます。ワクチンを接種した方が病気にかかることを予防したり、人に感染させてしまうことで社会に病気がまん延してしまうのを防ぐことを主な目的としています。また、病気にかかったとしても、ワクチンを接種していた方は重い症状になることを防げる場合があります。また、赤ちゃんがお母さんから受け継いだいろいろな病気に対する抵抗力(免疫)も、生後のある時期を過ぎると失われてしまいます。
このため、予防接種を受けて赤ちゃん自身に免疫をつくり、病気を未然に予防しましょう。
接種案内
- 丹波市役所より、お手元に届く通知書を必ずお確かめください。
- 対象者には、個別に通知されます。
- 通知した時期に受けられないときでも「制限年齢」までは受けることができます。
- 通知対象外で接種を希望する場合、必ず日程・時期等をお問い合わせください。
- 予防接種のことでご不明な点がありましたら、【丹波市健康課 電話:0795-88-5750】にお問い合わせください。
予防接種カードについて
丹波市では、平成29年4月より、市内受託医療機関で定期予防接種を受ける場合は、予防接種カードを使っての接種となります。予防接種カードは、『丹波市民』であり、『定期予防接種の対象者』であることを判断する重要なカードで、今後も定期予防接種を受ける際には必ず必要です。予防接種カードは、紛失防止のため、保険証や母子健康手帳といっしょにお持ちいただくことをおすすめします。
令和6年度より新型コロナ予防接種についても秋冬接種(定期予防接種)へ加わりました。
予防接種(小児)
| 初回開始年齢 | 接種回数 | 間隔 |
|---|---|---|
| 標準 生後2月から生後7月に至るまでの間 |
計4回 (初回3回、追加1回) |
初回接種については27日以上の間隔をおいて3回、追加接種については初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて、生後12月に至った日以降において、1回行う。 ただし、初回接種のうち、初回2回目及び3回目の接種は、生後24月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わない。(追加接種は可能。) 初回接種のうち2回目の注射は生後12月に至るまでに行う。それを超えた場合は、初回接種のうち3回目の注射は行わない。(追加接種は可能。) |
| 生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間 | 計3回 (初回2回、追加1回) |
初回接種については27日以上の間隔をおいて2回、追加接種については初回終了後60日以上の間隔をおいて、生後12月以降に1回おこなう。ただし、初回接種のうち、2回目の注射は、生後24月に至るまでの間に行うこととし、それを超えた場合には行わない。(追加接種は可能。) |
| 生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまで | 計2回 (初回1回、追加1回) |
60日以上の間隔をおいて2回行う。 |
| 生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者 | 計1回 |
- ヒブ
-
ヘモフィルスインフルエンザ菌b型という細菌によって引き起こされる病気で、そのほとんどが5歳未満で発症します。
主に気道の分泌物により感染を起こし、症状がないまま菌を保有(保菌)して日常生活を送っている子どもも多くいます。中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎などの表在性感染症の他、肺炎、敗血症、髄膜炎などの重い病気を引き起こすことがあります。 - ジフテリア
-
ジフテリア菌の飛沫感染で起こります。
感染は主にのどですが、鼻にも感染します。『偽膜』という膜ができて窒息することもあります。発病から2〜3週間には菌の出す毒素によって心筋障害や神経まひを起すこともあります。 - 百日せき
-
百日せき菌の飛沫感染で起こります。
風邪のような症状で始まり、続いて咳がひどくなります。乳幼児は咳で呼吸ができず、チアノーゼやけいれんが起こることがあります。 - 破傷風
- 破傷風菌やヒトからヒトへ感染するのではなく、土の中にいる菌が傷口からヒトの体内に入ることによって感染します。さまざなな神経症状(けいれんや手足の硬直、呼吸まひなど)があらわれ、発病の約2割が命を落とすといわれています。
- ポリオ
- ポリオは小児まひとも呼ばれています。かかっても無症状か、風邪に似た症状ですむ場合がほとんどですが、症状が出る場合は熱が下がった後に手足等にまひを生じます。
| 対象者 | 間隔 | 回数 | |
|---|---|---|---|
| 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 第1期初回 | 生後2月に達した時から生後7月に達するまでの期間 20日から56日の間隔をあけて |
3回接種 |
| 第1期追加 | 第1期初回接種終了後6月から18月までの間隔をおく | 1回 | |
注意点
過去に四種混合ワクチン、ヒブワクチンを接種されている方で未完了の場合、五種混合ワクチンは接種せず、従来と同一のワクチンを接種してください
重症急性胃腸炎で入院する原因としては最も多いと言われています。生後すぐに感染する場合もあり、ワクチンの接種は早い時期に完了させます。ロタウイルス胃腸炎の重症化を予防します。
令和2年10月1日から定期接種に含まれることになりました。(令和2年8月1日以降に生まれたお子さんが対象。)
| ワクチン名 | ロタリックス | ロタテック |
|---|---|---|
| 接種時期 |
|
|
| 接種回数 | 2回接種 (27日以上の間隔をあけます。) |
3回接種 (27日以上の間隔をあけます。) |
ヘモフィルスインフルエンザ菌b型という細菌によって引き起こされる病気で、そのほとんどが5歳未満で発症します。
主に気道の分泌物により感染を起こし、症状がないまま菌を保有(保菌)して日常生活を送っている子どもも多くいます。中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎などの表在性感染症の他、肺炎、敗血症、髄膜炎などの重い病気を引き起こすことがあります。
現在、わが国で接種されているヘモフィルスインフルエンザb型ワクチンは、乾燥ヘモフィルスb型ワクチンです。
ワクチン接種により、Hibが血液や髄液から検出されるような重いHib感染症にかかるリスクを95%以上減らすことができると報告されています。
| 初回開始年齢 | 接種回数 | 間隔 |
|---|---|---|
| (注意)標準生後2月から生後7月に至るまでの間 | 計4回 (初回3回、追加1回) |
初回接種については27日(医師が必要と認めた場合には20日)以上、標準的には27日から56日までの間隔をおいて3回、追加接種については初回接種終了後7月以上、標準的には7月から13月までの間隔をおいて1回行う。ただし、初回2回目及び3回目の接種は、生後12月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わない。(追加接種は可能。) |
| 生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間 | 計3回 (初回2回、追加1回) |
初回接種については27日(医師が必要と認めた場合には20日)以上、標準的には27日から56日までの間隔をおいて2回、追加接種については初回接種終了後7月以上、標準的には7月から13月までの間隔をおいて1回行う。ただし、初回2回目の接種は、生後12月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わない。(追加接種は可能。) |
| 生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまで | 計1回 |
- ジフテリア
- ジフテリア菌の飛沫感染で起こります。
感染は主にのどですが、鼻にも感染します。『偽膜』という膜ができて窒息することもあります。発病から2〜3週間には菌の出す毒素によって心筋障害や神経まひを起すこともあります。 - 百日せき
- 百日せき菌の飛沫感染で起こります。
風邪のような症状で始まり、続いて咳がひどくなります。乳幼児は咳で呼吸ができず、チアノーゼやけいれんが起こることがあります。 - 破傷風
- 破傷風菌やヒトからヒトへ感染するのではなく、土の中にいる菌が傷口からヒトの体内に入ることによって感染します。さまざなな神経症状(けいれんや手足の硬直、呼吸まひなど)があらわれ、発病の約2割が命を落とすといわれています。
- ポリオ
- ポリオは小児まひとも呼ばれています。かかっても無症状か、風邪に似た症状ですむ場合がほとんどですが、症状が出る場合は熱が下がった後に手足等にまひを生じます。
| 対象者 | 標準的な接種期間 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1期初回及び第1期追加 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 (補足)令和5年4月から、対象年齢が従来の生後3月から、生後2月に繰り上がりました。 |
第1期初回 生後2月に達した時から生後12月に達するまでの期間 | 20日から56日の間隔をあけ3回接種 |
| 第1期追加 第1期初回接種終了後12月から18月までの間隔をおく | 1回接種 |
注意点
過去に三種混合ワクチン、生ポリオワクチンを接種されている方で未完了の場合、未完了分は、90月に達するまでの間に四種混合ワクチン(または不活化ポリオ単独ワクチン)で接種します。
- 結核について
- 結核は、結核菌という細菌が体の中に入ることによって起こる病気です。結核菌は主に肺の内部で増えるため、せき、たん、発熱など風邪のような症状を呈することが多いですが、肺以外の臓器がおかされる場合もあります。
特に小児では症状があらわれにくく、全身に及ぶ重篤な結核につながりやすいため、注意が必要です。 - BCGワクチンについて
- BCGは、ウシ型結核菌を弱めた生ワクチンで、結核菌による感染を防ぐために行います。
日本の結核患者の発生率はアメリカの4倍ほどあるにも関わらず、小児におけるそれはアメリカの数値を下回っており、その一因として BCG接種の効果が考えられています。
| 対象者 | 標準接種期間 | 回数 |
|---|---|---|
| 生後1歳に至るまでの間にある小児 | 生後5月に達した時から生後8月に達するまで | 1回 |
- 副反応と注意点
- 接種後、10日ころに接種局所に赤いポツポツができ、一部に小さいウミが出来ることがあります。この反応は、接種後4週間ころに最も強くなりますが、その後かさぶたが出来て接種後3カ月ころまでには治り、小さな傷あとが残るだけになります。これは異常反応ではなく、免疫がついた証拠ですので、バンソウコウなどを貼らずすのまま清潔に保ってください。ただし、3カ月を過ぎても接種のあとがジクジクしているときは、かかりつけ医に相談してください。
副反応としては、接種した側のワキの下のリンパ節が腫れることがまれにあります。そのまま様子をみてかまいませんが、ただれたり、大きく腫れたり、化膿してウミが出るなとしたときは、かかりつけ医に相談しましょう。
もし接種後10日以内に、コッホ現象(接種部位の局所反応が早く、また強く出る)がみられた場合は、接種前に結核菌に感染している可能性がありますので、すみやかにかかりつけ医に相談してください。
対象は平成28年4月1日以降に生まれた方で、1歳のお誕生日の前日までに3回接種します。
- B型肝炎ワクチンとは?
-
B型肝炎は、B型肝炎ウイルスの感染によって起こる肝臓の病気です。
B型肝炎ウイルスへの感染は、一過性の感染で終わる場合と、そのまま感染している状態が続いてしまう場合(キャリアといいます)があります。キャリアになると慢性肝炎になることがあり、のうち一部の人では肝硬変や肝がんなど命に関わる病気を引き起こすこともあります。
ワクチンを接種することで、体の中にB型肝炎ウイルスへの抵抗力(免疫)ができます。この免疫が出来ることで、一過性の肝炎を予防できるだけでなく、キャリアになることを予防でき、まわりの人への感染も防ぐことが出来ます。
(注意)予防接種を受けても、お子さんの体質や体調によって免疫が出来ないことがあります。
ワクチンの種類は2種類あります。(いずれも不活化ワクチン)
ビームゲン(製造販売元:財団法人化学及血清療法研究所)
ヘプタバックス(製造販売元:MSD株式会社)
(注意)ラテックスアレルギー(天然ゴム製品…炊事用手袋、バンソウコウ、ゴム風船などに接触することによって起こるじんましん、ぜんそく発作などの即時型アレルギーのこと)のあるお子さんは、接種する前に主治医にご相談ください。(ヘプタバックスを選択した方のみ)
| 対象者 | 標準接種期間と回数 |
|---|---|
| 平成28年4月1日以降に生まれた方で生後1歳に至るまで(1歳の誕生日の前日まで)の方 (標準接種期間・生後2月に達した時から生後9月に達するまでの期間) |
1歳の誕生日の前日までに3回接種します。 2回目の接種は、1回目の接種から27日以上の間隔をあけて接種します。 3回目の接種は、1回目の接種から139日以上の間隔をあけて接種します。 (たとえば、1回目を水曜日に接種した場合、2回目は1回目から4週後の水曜日から、3回目は1回目から20週後の水曜日から誕生日の前日までに接種します。) |
(注意)母子感染予防のためにHbs人免疫グロブリンと併用してB型肝炎ワクチンの接種を受けておられる方は、健康保険が適応されるため、この制度の対象ではありません。
空気感染、飛沫感染、接触感染により広がり、その潜伏期間は感染から2週間程度と言われています。
発疹の発現する前から発熱が認められ、典型的な症例では、発疹は紅班(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿胞(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒するとされています。
一部は重症化し、小児における重症化は、熱性けいれん、肺炎、気管支炎等の合併症によるものです。
| 対象者 | 回数 |
|---|---|
| 生後12月から36月に至るまでの間にある者(1歳から3歳の誕生日の前日まで) 標準的な接種年齢 1回目の接種:生後12月から15月に至るまでの間 2回目の接種:初回接種終了後、6月から12月に至るまでの間隔をおく |
2回 |
(注意)すでに水痘(水ぼうそう)にかかったことが確実なお子さんは対象外になります。
ヒトから直接ではなく、ブタなどの体内で増えたウイルスが蚊によって媒介され感染します。
7日から10日の潜伏期間のあと、高熱、嘔吐、意識障害、けいれんなどの症状を示す急性脳炎になります。一般に日本脳炎ウイルスに感染した場合、およそ1,000人に1人が日本脳炎を発症し、発症した方の2割から4割が亡くなってしまうと言われています。また神経の後遺症を残す人が多くいます。
| 対象者(標準的接種期間・回数) | |
|---|---|
| 第1期初回 | 生後6月から90月に至るまでの間に、6日以上の間隔をおいて2回 (標準的には、3歳から4歳の間に、6日から28日までの間隔をおいて2回) |
| 第1期追加 | 生後6月から90月に至るまでの間に、第1期初回接種終了後6月以上の間隔をおいて1回 (標準的には、4歳から5歳の間に、第1期初回接種終了後1年を経過した時期に1回) |
| 第2期 | 9歳以上13歳未満に1回 (標準的には、9歳から10歳の間に、1回) |
- 日本脳炎の予防接種の救済措置について
-
平成23年5月20日から日本脳炎の定期予防接種の一部が変更になり、平成17から21年度の間に定期予防接種の機会を逃した方々への接種時期が緩和されました。
- 平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方
20歳未満の間、未接種分を定期予防接種として受けることができます。
ただし、平成14年4月1日以前に生まれた方には、予防接種カードを交付しておりませんので、接種をご希望の場合は事前に申請してください。 - 平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方
平成28年4月から、90月(7歳6ヵ月)に至るまでの間に1期の3回接種を完了できなかった場合でも、不足している回数を2期の対象年齢(9歳以上13歳未満)の間に定期接種として受けられるようになりました。
- 平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方
- ジフテリア
- ジフテリア菌の飛沫感染で起こります。
感染は主にのどですが、鼻にも感染します。『偽膜』という膜が出来て窒息することもあります。発病から2〜3週間後には菌の出す毒素によって心筋障がいや神経まひを起こすこともあります。命を落とすこともあるといわれています。 - 破傷風
- 破傷風菌はヒトからヒトへ感染するのではなく、土の中にいる菌が傷口からヒトの体内に入ることによって感染します。さまざまな神経症状(けいれんや手足の硬直、呼吸まひなど)があらわれ、命を落とすこともあるといわれています。 ジフテリア、破傷風の2つの病気対するワクチンが1つになったものです。
| 対象者 | 回数 |
|---|---|
| 11歳以上13歳未満(標準として、11歳から12歳に達するまで)に | 1回 |
子宮頸がんのほとんどはヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの感染が原因です。
| 対象者 | 回数 |
|---|---|
| 小学校6年〜高校1年生相当年齢の女子 (標準的な接種時期は中学1年生) |
1回 |
- 接種ワクチン・スケジュール
- 令和5年4月1日から、シルガード9(9価)が対象ワクチンとして追加され、従来からあるサーバリックス(2価)と、ガーダシル(4価)を含めて、3種類のワクチンの中から選択できるようになりました。3回とも同じワクチンで接種しますが、すでにサーバリックスまたはガーダシルを1回または2回接種している方が、医師と相談の上、シルガード9に変更することも可能です。
なお、サーバリックスまたはガーダシルの接種回数は3回ですが、シルガード9については1回目の接種開始年齢によって接種回数が異なりますのでご注意ください。(15歳未満で1回目を接種した場合は2回、15歳以上で接種開始した場合は3回)
| ワクチンとスケジュール | |||
|---|---|---|---|
| 頻度 | サーバリックス(2価) | ガーダシル(4価)シルガード9(9価)(注意)1回目の接種開始年齢が15歳以上 | シルガード9(9価)(注意)1回目の接種開始年齢が15歳未満 |
| 標準的な間隔 | 1月以上の間隔を置いて2回接種した後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回。(計3回) | 2月以上の間隔を置いて2回接種した後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回。(計3回) | 1回目の接種から6月の間隔をおいて1回。(計2回) |
| 標準的な接種方法をとることができない場合 | 1月以上の間隔を置いて2回接種した後、1回目の接種から5月以上、かつ2回目の接種から2月半以上の間隔をおいて1回。 | 1月以上の間隔をおいて2回接種したあと、2回目接種から少なくとも3月以上の間隔をおいて1回。 | 1回目と2回目の接種は、通常5月以上の間隔をおいて1回。5月未満である場合は、3回目の接種が必要。 |
- 麻しん
- 麻しんウイルスの空気感染によって起こります。「はしか」としてよく知られ、予防接種のないころには感染力が強いため、ほとんどすべての子どもがかかり、年間1万人の死亡数もあったことのある重症感染症です。
潜伏期間は約10日から12日で、発疹を認め、高熱を伴います。合併症は約40%に認め、肺炎、気管支炎、中耳炎、脳炎などがあり、脳炎の合併症は患者約1,000人に1から2人の割合で発生します。
また、予防接種をうけずに麻しんにかかった人は、約千人に1人の割合で死亡すると言われています。 - 風しん
- 風しんウイルスのの飛沫感染によって起こり、潜伏期間は2から3週間です。軽い風邪症状ではじまり、発疹、発熱、首や耳の後ろのリンパ節の腫れなどが主症状です。発疹も熱も3日程度で治るので、『3日ばしか』と呼ばれることもあります。
妊婦が妊娠初期にかかると、先天性風しん症候群と呼ばれる病気により、心臓病、腎臓病、白内障、聴力障がいなどの障がいをもった児が生まれる可能性が高くなります。
風しんは、麻しんに比べると比較的軽症ですが、近年成人の間で流行し、問題となっています。
| 対象者 | 回数 | |
|---|---|---|
| 1期対象者 | 生後12月から24月に至るまでの間にある者(2歳の誕生日の前日まで) | 1回 |
| 2期対象者 | 5歳から7歳未満(小学校就学前の1年間)の者 令和6年度対象者:平成30年4月2日〜平成31年4月1日生まれ | 1回 |
予防接種(一般成人〜高齢者)
- 〇帯状疱疹とは
-
帯状疱疹は、多くの人が子どもの時に感染する水痘(水ぼうそう)のウイルスが原因で起こります。水ぼうそうが治った後も、ウイルスは脊髄から出る神経節という体の部分に潜んでおり、加齢や過労、ストレスなどで免疫力が低下すると、ウイルスが再び活動を開始して、帯状疱疹を発症します。50歳以上から発症率が上昇していくと言われています。
体の左右どちらかの神経に沿って、痛みを伴う赤い斑点と水ぶくれが多数集まって帯状に皮膚症状が出ることが多く、通常、皮膚症状に先行して痛みが生じます。多くの場合、皮膚症状が治まると痛みも消えますが、その後も痛みが残ることもあります。また、帯状疱疹が現れる部位によっては、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などの合併症を引き起こすことがあります。
発症してしまった場合は、医療機関を受診し、早めに治療を開始することが大切です。
助成事業の内容
助成対象(いずれも該当する方)
- 接種日時点で、丹波市に住民登録のある50歳以上の方
- 過去にこの制度による助成を受けていない方
助成制度のご利用については、いずれか一方のワクチンにのみ適用されます。
| 使用ワクチンと助成方法 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン 「ビケン(生ワクチン)」 | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 「シングリックス(不活化ワクチン)」 |
助成回数と助成額 | 1回 / 4,000円 | 2回 / 1回あたり10,000円 |
(注意)シングリックスについては、帯状疱疹に罹患するリスクの高い18歳以上の方も接種対象者として認められていますが、今回の助成の対象には含まれません。
- ワクチンの種類
- 帯状疱疹ワクチンは2種類あり、接種方法や回数が異なります。下記の表を参照ください。
| 帯状疱疹ワクチンの種類 | ||
|---|---|---|
| 種類 | ビケン (生ワクチン) | シングリックス (不活化ワクチン) |
| 予防効果 | 約50〜60% | 50歳以上では97.2% 70歳以上では89.8% |
| 持続期間 | 接種から約5年程度 | 接種から約10年程度 |
| 副反応 | 局所反応(約50%) 全身反応(約4%) | 局所反応(約80%) 全身反応(約60%) |
| 接種回数 | 1回 | 2回 【2か月間隔】 |
| 接種費用 | 8,000円 | 1回あたり22,000円 |
| 自己負担額 | 4,000円 | 1回あたり12,000円 |
(注意)「シングリックス」は基本2か月間隔で、遅くとも6か月までに2回目を接種します。6か月を超えて接種した場合、公費助成の対象外となり、全額自己負担(22,000円)となりますので、ご注意ください。
- 注意事項
-
- 水痘ワクチンによる強いアレルギー症状(アナフィラキシーなど)を起こしたことがある方は接種できません。
- 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する方、および化学療法やステロイドなど免疫力抑制をきたす治療を受けている方は接種できません。
- 妊娠している方、授乳中の方は接種できません。また、ワクチン接種後に妊娠の予定がある方は、接種可能な時期等について医師とご相談ください。
- 50〜64歳の方で予防接種をされる場合
-
- 予防接種を受けられる前に、必ず、健康課または各支所にて助成券の申請手続きをします。即日交付を希望される方は、健康課で申請してください。
- 市から交付される予防接種助成券を受け取ったのち、丹波市内の実施医療機関で接種を受けてください。
- 接種後、医療機関に自己負担額をお支払いください。
- 65歳以上の方で予防接種をされる場合
- 丹波市で交付している「予防接種カード」を助成券としてご利用いただけます。予防接種カードを丹波市内の実施医療機関に持参し、接種後、自己負担額を医療機関にお支払いください(助成券の事前申請は不要です)。
- 申請に必要な書類
-
- 丹波市帯状疱疹予防接種助成申請書
- 本人確認ができるもの(例:マイナンバーカード・保険証・運転免許証等)
郵送の場合は、申請書と本人確認書類のコピーを同封してください。
助成券申請の受付場所
月曜〜金曜(祝日・年末年始除く) 午前8時30分〜午後5時15分
- 健康課…即日発行
- 各支所…後日郵送(申請より約1週間程度かかります)
| 対象者 | 接種回数・接種量 | 自己負担金 |
|---|---|---|
| 接種日時点で65歳の方 | 1回のみ 0.5ミリリットル | 自己負担金 2,400円 接種対象者で接種を希望される方は、市の交付する予防接種カードを受託医療機関に提示することにより、接種費用の一部を市が負担します。(1人1回のみ) |
| 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害で身体障がい者手帳1級を有する方 |
注意(対象者の変更)
昨年までは、5歳ごとに未接種者(例 70歳、75歳、80歳等)においても対象とする経過措置がありましたが、令和6年度から国の制度改正に伴い終了しました。
 接種当日、医療機関にもっていくもの
接種当日、医療機関にもっていくもの市より配布の予防接種カード
頭に双葉が生えているキャラクターの描かれた丹波市予防接種カードの見本
(補足)生活保護受給者で接種を希望される場合は、お持ちの「予防接種カード」と「生活保護受給者票」を医療機関に提出してください。(自己負担が無料になります。)
そのため、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を風しんの定期接種の対象者とし、平成31年4月から3年間制度を実施していましたが、制度の期間延長により、令和4年度から更に3年間継続して実施されることとなりました。
まだ風しん抗体検査・予防接種を受けられていない方につきましては、健康課に申請していただくことによって、クーポン券を送付させていただきます。
クーポン券が届きましたら、抗体検査(血液検査。無料)または予防接種(無料)を受けてください。なお、予防接種については、抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方(検査結果が陰性)に限り、麻しん風しん予防接種(無料)を受ける対象となります。
| 対象者 | 回数 |
|---|---|
| 丹波市に住民票のある昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性のうち、今まで、成人風しん抗体検査・予防接種の制度をご利用でない方。 | 1回 |
接種する前に接種を受ける方の同意がある場合に限り、接種を行います。
ワクチンの接種を受ける方には、接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解したうえで、自らの意思で接種を受けていただきます。
受ける方の同意がないまま、接種が行われることはありません。
令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種について
令和6年3月31日までは、「特例臨時接種」として、全額公費(自己負担なし)により実施していましたが、令和6年4月1日以降は、季節性インフルエンザワクチン接種と同様の「B類疾病の定期接種」として実施され、接種費用は有料(一部公費負担あり)となります。
「特例臨時接種」と「B類疾病の定期接種」の比較
予防接種法上の「特例臨時接種」から、季節性インフルエンザと同様の「B類疾病の定期接種」に位置付けられ、以下のとおり制度が変更される予定です。
なお、これらの情報は現時点のものであり、国の方針次第では変更となる場合があります。
| 比較表 | ||
|---|---|---|
| 令和6年3月31日まで (令和5年秋開始接種) | 令和6年4月1日から (季節性インフルエンザの定期接種と同様) |
|
| 接種の分類 | 特例臨時接種 | B類疾病の定期接種 |
| 対象者 | 生後6か月以上 |
|
| 接種期間・回数 | 期間:令和5年9月20日〜令和6年3月31日 回数:(追加)1回 (初回)年齢・使用ワクチンで異なる | 期間:令和6年の秋〜 回数:1回 |
| 接種勧奨の有無 | あり 65歳未満の方(基礎疾患を有する者等を除く)に対しては、なし | なし |
| 努力義務の有無 | あり 65歳未満の方(基礎疾患を有する者等を除く)に対しては、なし | なし |
| 自己負担 | あり(全額国費で負担) | 一部自己負担あり(2100円) |
| 使用するワクチン | ファイザー社、モデルナ社、武田社、第一三共社 | WHOの推奨株を用いる事を基本とする |
| 接種券の送付 | あり | なし(予防接種カードを使用) |
| 予防接種証明書 |
| ワクチン接種後に接種医療機関で交付 3月31日までの接種分は健康課で交付 (申請は市役所窓口で可能) |
| 健康被害救済制度 | 予防接種法に基づき、A類・臨時接種の枠組みで実施 | 予防接種法に基づき、B類の枠組みで実施 |
任意接種
令和6年4月1日以降に、定期接種の対象とならない方・定期接種の期間外に接種を希望される方は、任意接種として接種を受けることができます。費用は全額自己負担となります。
- 接種の受け方
-
接種費用の助成を受けるには、丹波市で発行している「予防接種カード」の提示が必要です。市内の医療機関で予防接種を受ける際には、必ずお持ちいただくようお願いします。
- 市内の実施医療機関で予約をします(予約不要の医療機関もあり)。
- 接種日当日は、必ず予防接種カードを持参し、接種を受けてください。
- 接種後、医療機関に自己負担額をお支払いください。
該当の方は、丹波市健康課(健康センターミルネ2階)で申請を行ってください。
また、申請の際には「本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)」と「身体障害者手帳(1級)」を必ずお持ちいただくようお願いします。
【小児】
10月1日より、生後6か月から中学生相当のお子さまに向けて、季節性インフルエンザワクチンの予防接種費用の一部を助成いたします。秋冬にかけてウイルスが流行しやすくなるため、予防接種を受けて免疫力を高めておくことが重要です。秋からの予防接種について
- 接種対象
- 接種日時点で、丹波市に住民登録のある生後6か月から中学3年生までの方
- 接種対象者と自己負担額
-
1回目の接種 対象者 自己負担額 6か月児〜中学生 2,900円 2回目の接種 対象者 自己負担額 6か月児〜13歳未満(1回目の接種時において、13歳未満の方) 2,900円 (注意)1回目の接種時において13歳未満の場合、接種回数は2回です。
2回接種の場合、接種間隔は2週から5週未満です。接種間隔が5週を超過した場合は、公費助成の対象となりませんのでご注意ください(医学的な理由がある場合、その理由が解消されたのち、すみやかに接種申し立てを行った場合を除く)。
【高齢者】
10月1日より、65歳以上の方に向けて、季節性インフルエンザワクチンの定期接種を開始いたします。秋冬にかけてウイルスが流行しやすくなるため、予防接種を受けて免疫力を高めておくことが重要です。接種日時点で、丹波市に住民登録のある65歳以上の方
(注意)60歳から64歳の方で、心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全の機能障害により身体障害者手帳1級をお持ちの方についても、今回の定期接種の対象となります。
- 接種対象者と自己負担額
-
接種費用
区分 対象者 自己負担額 (1) 65歳以上(接種日当日に65歳以上の方) 1,400円 (2) 60歳〜64歳の方で心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスの機能障害により「身体障害者手帳1級」をお持ちの方 1,400円 (3) (1) (2)のうち、生活保護費受給者の方 無料 (注意)(3)の方は、医療機関へ「生活保護受給者証」の提示が必要です。
接種回数対象者 回数 (1)〜(3)の方全て 1回限り 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンについては、医師が必要と認める場合には、同時接種が可能です。新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種を希望される場合は、事前に接種を希望する医療機関へご相談ください。
なお、インフルエンザワクチンは他のワクチンとの接種間隔の制限はありません。
- 接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について
-
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずることがあり、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するため、予防接種健康被害救済制度が設けられてます。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により医療費・障害年金等の給付が行われます。
新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
病気にかかっているときや、特に熱があるときの予防接種はみあわせてください。
当日は、予防接種カードを忘れずにご持参ください。(お子様の場合は母子健康手帳もお持ちください。)
予防接種カードを紛失・破損された場合は、丹波市健康課までお問合せをお願いします。